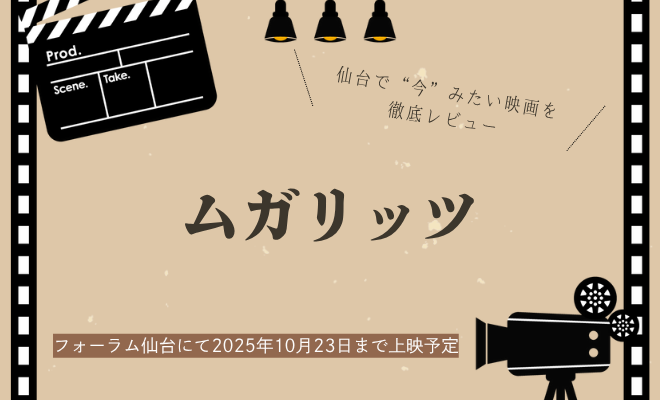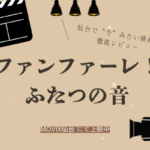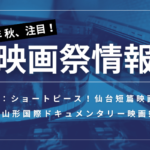グルメ案件お待ちしています。
今回の映画は2025年10月23日までフォーラム仙台で上映中の「ムガリッツ」(監督:パコ・プラサ)。美味しんぼと東海林さだおのエッセイで育った筆者による、食に関する映画レビューです。
スペイン・バスク地方にあるミシュラン二つ星のレストラン、ムガリッツを追ったドキュメンタリーである。原題のサブタイトル(およびポスターのコピー)にあるように、その料理は独特である。
なんといっても、最後まで見終わっても「これは美味しいだろうな」という想像がつかない。それを言い表す言葉が、自分の中になさそうだ。また、(フォークやナイフすらない)テーブルに備え付けられた冊子を怒りのあまり破っていった客のエピソードが示すように、このレストランが絶賛されるのみでないことは事実のようだ。
スズキ、エビ、バカラオ、ウニ、ラムチョップ、コンソメ、納豆、昆布、茶葉、コンブチャ、蜂蜜、カッテージチーズ、蜂の子……
わりと日本食のものも多い、食材だけを並べてみるとなんとなくわかる気がしないでもないのだが、調理風景を見るとその朧げな直感はあっという間に消える。試食では「ハードコア」という感想が出たりするような料理(「食事」でもありつつ、現代美術の鑑賞のようでもある)、それはおそらく想像のはるか向こう側にある、未知の味覚なのだろうとは思いつつも。
そしてそれを創り出す人々の様子も、レストランと聞いて想像する状況からはかなりかけ離れている。まず冒頭でも説明されるが、毎年11月から翌年4月までレストランは閉店する。スタッフたちはひたすら、メニュー開発を行うためだ。映画では、主にその様子を追っている。
「目に見えないもの」というテーマがオーナーシェフによって提示され、それに沿って開発研究チームがメニューを考案していく。メインビジュアルにあるように食材・サブテーマが書かれたイラストが貼り出され、ホワイトボードには概念図が書かれ、形から食べ物をデザインし、食材を得るために養蜂場やレストランの畑に行き……という開発の様子、あまりに多くの回数の試作を、あまりに多くの人数・チーム(メンバーそれぞれにさまざまな背景があることが終盤でそれとなくわかる)で行なっている光景は、過酷であると同時に楽しそうでもある。上手く言えないが、すぐそこに文化祭が迫っているかのような毎日。もちろん、レストランにはそれだけでなく、メニューや「言葉の定義」を書いた(先述の客が破り去った)冊子を作るクリエイティブ・チームたちもいる。
その一方で、オーナーシェフが出てくることは少ない。彼が「リーダーシップ」についてインタビューされている際も、そのような批判はある、としつつも、「師匠がやるべきことは弟子の不安を汲み取ること」であり、「最終決定をしない」と答えるような組織がこのレストランなのだ。
彼らは「遊ぶために遊べ」という、一見容易に見えて実現がとてつもなく難しい、至上ともいえる命題を与えられている。そんな、まさに「創造」といえる日々に格闘し続ける様子を映したのがこのドキュメンタリーである。その世界をぜひ味わってみてほしい。
余談:ホラーファンなら、監督名で思い出すことがあるかもしれない。ただこの映画にはそういった要素はない。
余談その2:ある種『めしにしましょう』シリーズ(作:小林銅蟲)を思い出す部分がある。食に対する、あまりにも大きい情熱……